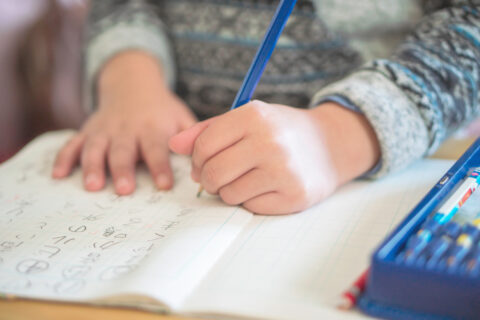目次
こんにちは。
SOLE個別最適学習ラボ編集部です。
お子様の進路や学校選びはどのご家庭にとっても大きな関心ごとでしょう。
とくに、発達特性のあるお子様の場合、
「この子に合った環境はどこだろう」
「将来に向けて、今どのような選択をするべきだろう」と
悩まれることもあるかと思います。
今回は、進路選択や学校選びの際に覚えておいてほしい視点やおさえておきたいポイントについてまとめています。
気になる私立高校無償化についてや合理的配慮の実例のご紹介(大阪府)もさせていただきます。
発達に凸凹のある子どもたちの進路選びのポイント
発達に特性のあるお子様を育てる中で、進路について考えていると不安に包まれることがあるかもしれません。
周りと比べてしまったり、情報の多さに戸惑ったりすることも少なくないと思います。
ここで、進路を考えるうえで大事にしておきたいポイントを取り上げながら、お子様の未来に向けてできることを一緒に考えていきましょう。
子どもの意思を尊重すること
まず第一に、子どもの意思を尊重することです。
進路を考えるとき、どうしても親の目線で「安心できる場所」や「向いていそうな進路」を選びたくなってしまうものです。
しかし、どれだけ環境が整っていても、そこに「自分で選んだ」という感覚がなければ、うまくいかなかったときにその道を前向きに受けとめることが難しくなります。
たとえ迷いながらの選択であっても、動機は些細なことでも、自分で考え決めたという経験はのちの成長や気づきにつながっていきます。
特性を理解して選択肢を広げること
「うちの子に進学なんてできるのかな」「受験は難しいかもしれない」
そのように思ってしまうことは決して珍しいことではありません。
しかし、発達の特性がある子どもたちにもその子に合った方法があります。
最近では、読み書きに困り感のある子どもに対して、受験でパソコンの使用や別室受験といった「合理的配慮」を行う学校も増えてきました。
入学してからもノートテイクは板書を写真にとって読み込む、穴埋めのプリントにするなどがOKである学校もあります。
試験の方法も、学力試験ではなく通知表の評定をもとに選抜を行う学校、面接や作文、実技で評価してくれる学校もあります。
また、通信制高校やサポート校など偏差値でははかれない魅力をもつ学校もあります。
できないことが目立ってしまいがちですが、「どんな環境であれば力を発揮できるか」「どのようなサポートがあれば安定して過ごせるか」という点を整理すると、「ゆっくり自分らしく学べる」ことを大切にしている学校にめぐりあえるのではないでしょうか。
特性を前提にあきらめるのではなく、特性を理解して活かせる環境を探すという視点をもちながら、お子様にとってのベターな選択を探していきましょう。
早めに相談・準備すること
発達に特性のあるお子様の進路選びは、早めに動きだすことで気持ちにも余裕が生まれます。
「まだ早いかも…」と思っているうちに、あっという間に中学・高校・その先の進路を考えるタイミングがやってきます。
前述しましたが、進学先がお子様の特性にあった環境かを見極めるためにも、時間をかけて情報を集めたり、見学に行ったりすることが欠かせません。
また、学校の先生や特別支援教育コーディネーター、発達支援の専門家など、周囲に相談することも大きな助けになります。
自分たちだけでは気づけない視点を得られることもありますし、何より「その子にあった選択肢」を一緒に考えてくれる人がいることは大きな安心材料となるでしょう。
進路について不安を感じている方こそ、早めに一歩踏み出してみてください。
「将来どのような形で力を発揮できそうか」を少しずつ考えていけるといいですね。
偏差値によらない中学受験
中学受験というと、つい偏差値で学校を選んでしまいがちですが、今はそれだけではありません。
大阪府の私立高校の無償化が進んだことで、進路の選択肢も広がり、学び方や支援体制を重視して学校を選ぶご家庭も増えています。
発達特性のあるお子様にとって、「何をどう学ぶか」「どのような配慮が受けられるか」は進学先を見つける大きなヒントになります。
私立高校無償化(大阪府)
中学受験のニーズが増えた背景には、大阪府の「私立高校の授業料無償化制度」が関わっている場合があります。
以下に簡単にご説明いたします。
大阪府では公立高校だけでなく私立高校の「授業料の実質無償化」がすすんでいます。
私立高校は学費が高いイメージがありますが、大阪府に住んでおり条件を満たした世帯であれば授業料がほとんどかかりません。
無償化制度はいつから?
2024年度から段階的に拡大されてきており、2026年度以降は、全ての家庭で授業料が実質無料になる予定です。
どんな家庭が対象?
現在(2025年度時点)は、年収910万円未満の世帯が対象です。
この場合、私立高校の年間授業料(最大約63万円)がほぼ全額支給されます。
※2026年度以降はこの所得制限もなくなる予定なので、より多くのご家庭が対象になります。
授業料以外にかかる費用は?
この制度でカバーされるのは授業料のみです。
入学金や施設費、教材費、制服代、修学旅行などの費用は別途かかる場合があるので注意が必要です。
学校ごとに金額が異なることになるため、説明会などで事前に確認しておくとよいでしょう。
なぜ無償化?
大阪府がこの制度を始めたのは、「家庭の経済状況に関わらず、子どもが希望する高校に通えるようにする」ためです。
これによって、お子様に合った学校を選びやすくなりました。
参考リンク
得意不得意を知ってムダのない中学受験を
発達特性のあるお子様は、「すべての教科を平均的にこなす」ことが苦手な場合があります。
中学受験では、その得意不得意を踏まえた学習の取捨選択ができるのも大きなメリットといえるでしょう。
たとえば:
・国語が得意で算数が苦手な子
→記述力が重視される学校
・図形が得意な子
→パズル問題が試験に出る学校
・理科社会が難しい子
→2科目入試を実施している学校
このように、お子様の強みを生かす戦略が取りやすいのが中学受験の大きな特徴です。
もちろん、すべての学校で自由に選べるわけではありませんが、最近では適性検査型の入試など試験の形式も多様化しています。
さらに、中学受験を通して学校を選ぶことで、その子に合った授業スタイルや学び方の学校を選べるというメリットもあります。
たとえば:
・書くことが苦手な子にとって、iPadやPCを使ったデジタル学習をとりいれている学校は、ノートをとる負担を減らせるかもしれない
・集中力に波がある子には、少人数制でゆったりすすむ授業の学校があっているかもしれない
・得意な科目をグングン伸ばしたい子は、習熟度別の授業や探求学習が盛んな学校があっているかもしれない
このように、中学受験はただの成績勝負ではなく、お子様に合う環境を選ぶ手段の1つです。
その子らしく学べる場所を見つけることで、入学後の学校生活もずっと前向きになります。
中学校における合理的配慮
合理的配慮とは?
「合理的配慮」とは、発達特性を持つお子様が、他の子どもたちと平等に教育を受けられるように、試験や学習環境を調整することを指します。
これは、法的にも保障されている権利です。
特性別の具体的な配慮例
1. ASD(自閉スペクトラム症)のお子様
環境の調整:試験会場の事前見学や、静かな別室での受験を希望できる
コミュニケーションの配慮:面接の質問内容を事前に共有してもらう
2. ADHD(注意欠如・多動症)のお子様
時間の調整:試験時間の延長や、休憩時間の確保をお願いする
座席の配慮:試験中に集中しやすいよう、座席位置の変更を検討してもらう
3. LD(学習障害)のお子様
教材の工夫:問題用紙の文字サイズを大きくしたり、ルビを振ってもらう
試験形式の変更:口頭試問への変更や、記述式から選択式への変更をお願いする
合理的配慮を受けるためのステップ
医師の診断書を取得する:お子様の特性を明確にするため、専門医の診断書を準備する
志望校に相談する:受験を希望する学校に事前に相談し、配慮が可能か確認する
必要な手続きを行う:申請書類の記入と提出など、学校や試験機関が指定する手続きを期限内に行う
※特に診断書がない場合でも、過去の支援記録や学校での対応実績があれば、配慮を受けるための根拠として活用できる場合もあります。
参考までに、以下の情報源もご覧ください。
受験上の合理的配慮の具体例と大学進学について
つづいて、高校受験についてお伝えします。
最近は受験の方法が多様化し、合理的配慮を受けながらチャレンジできる進路が増えてきました。
ここでは、
・どのような受験方法があるのか
・高校受験での合理的配慮の具体例
・大学進学は必要なのか
ということについて簡単にまとめています。
受験方法のいろいろ
高校受験というと「学力試験」が中心のように感じられるかもしれませんが、現在は推薦入試や内申重視の選抜、通信制高校など、多様な選択肢が広がっています。
以下に主な受験方法とそれぞれの特徴をわかりやすくまとめました。
お子様に合った受験方法を見つける参考になれば幸いです。
① 一般入試(学力試験)
国語・数学・英語などのペーパー試験で合否が決まる方法です。
公立高校では2月〜3月に行われることが多く、学力勝負になるため、試験慣れしていないお子様には負担が大きくなる可能性も。
☞ 発達特性のあるお子様には、試験会場の緊張感や時間配分が課題になりやすいこともあります。
② 推薦入試(学校推薦型選抜)
在籍中学校からの推薦を受けて受験する方法で、調査書(内申点)・面接・作文などが中心になります。
都道府県によって時期や内容は異なりますが、1月ごろから実施されることが多いです。
公立高校では倍率が高く、面接が重視される傾向
私立高校では「単願推薦」など、内申条件を満たせば合格しやすいケース有
☞ 試験よりも日々の学校生活の様子が評価される点がポイントです。
③ 自己推薦・特色選抜
お子様自身が志望理由や将来の目標をアピールする方式です。
作文やプレゼン、面接などが行われます。
芸術やスポーツ、ICTなど「得意なこと」を活かせる学校も
書類選考が中心で、学力試験がない・または軽い学校も増加中
☞ 個性や努力の過程が評価されるため、試験が苦手なお子様にも向いています。
④ 内申重視の選抜(調査書選抜)
学力試験は行わず、通知表の成績や出席状況、生活態度などを中心に選抜する方式です。
私立高校で採用されることが多く、成績が安定していれば安心して受験できます。
☞苦手科目があっても、真面目な姿勢や努力が評価されるケースがあります。
⑤ 通信制高校・サポート校
試験がない、または面接のみなど、形式的な選抜にとどまる学校も多くあります。
自分のペースで学習できる
不登校経験や発達特性への理解がある学校が多い
サポート校と連携し、生活面や進路指導も手厚い
☞学校生活に不安があるお子様にも安心な環境が整っている場合があります。
大阪府 高校入試での合理的配慮の実例
大阪府の高校入試でも、発達特性に応じた「合理的配慮」を受けることができます。
大阪府の高校入試での過去の実例(高校)
① 大阪府立咲くやこの花高等学校(総合学科)
配慮内容:入試時における試験時間延長、別室受験、読み上げ対応など
背景:多様な生徒を受け入れる姿勢が強く、支援教育に理解がある
特色:面接重視の推薦入試あり。表現力や意欲を評価する方式もあるため、試験以外の面で力を発揮しやすい
② 大阪府立水都国際高等学校
配慮内容:別室での受験、静かな環境、読み書きの支援(配慮申請に応じて)
背景:国際バカロレアに準拠し、多様な背景を持つ生徒を対象にしているため、柔軟な対応が可能
備考:学力テスト以外にも、英語面接やプレゼンが評価対象になるため、得意を活かせる場面が多い
③ 通信制・定時制高校(例:大阪府立桃谷高校)
配慮内容:入試の学力試験における時間延長や、必要に応じた面談・支援の導入
特色:通信・定時制では、試験自体がシンプルであったり、受験相談の時点で柔軟な対応をしてもらえるケースも多い
大阪府の高校入試での過去の実例(生徒)
①:自閉スペクトラム症(ASD)+ADHDの男子生徒
申請内容:
・試験時間の延長(各教科10分)
・別室受験(静かな環境を希望)
・監督者1名による個別対応(声かけや進行の補助)
配慮が認められた理由:
学校でのWISC-IV検査の結果と、医師の診断書に「処理速度の著しい低下」「注意の持続困難」が記載されていたため。
進学先:府立総合学科高校(推薦入試を活用)
→ 面接では視線や表情の固さも考慮し、評価が不利にならないよう配慮。
②:限局性学習症(SLD/ディスレクシア)の女子生徒
申請内容:
・国語の文章を拡大印刷
・数学の文章題は読み上げ対応
・選択肢にマークする形式のプリント
根拠書類:
・教育相談所の心理士によるWISC・読み書き検査の結果
・小中学校の支援記録(特別支援教室での学習歴)
進学先:府立支援付き高校(チャレンジ支援校)
→ 入学後も読みの困難に対しICT支援あり。
③:感覚過敏が強いHSP傾向の生徒(診断はなし)
申請内容:
・別室受験のみ希望(集団環境が著しく不安)
・耳栓やノイズキャンセリングの使用許可
対応校の方針:
・医師の診断がなくても、担任とスクールカウンセラーの意見書があれば柔軟に対応する(※すべての学校がそうではない)
進学先:通信制高校(私立)
→ 面談時に校内見学を実施し、「ここなら通える」と本人が判断。
ただし、これらのような配慮を受けるためには、中学校を通じて事前に申請が必要です。
大阪府教育委員会では、毎年「入学者選抜における配慮事項について」という通知が出されます。
そして、11月ごろに「入学者選抜における配慮事項の申請」が締め切られます。
そのため、中学3年の1学期〜2学期の早い段階で、担任の先生や支援コーディネーターの先生にご相談ください。
また、最新の申請期限や様式については、中学校から配布される進路資料または教育委員会のWebサイトをご確認ください。
発達特性のある子どもの大学進学の必要性
発達に特性のあるお子様にとって、大学進学は「一つの選択肢」であり、将来の自立や就労に向けた準備期間として重要な意味をもつことがあります。
ただし、すべての子にとって必要不可欠というわけではなく、個々の特性や進路希望に応じた柔軟な判断が大切です。
大学進学が「プラス」に働く理由
・自分のペースで学べる時間と自由度
・時間割や履修を自分で調整できるため、疲れやすい子、集中力の波がある子にとっては過ごしやすい環境である
・興味のある分野に特化できる
・専門分野に集中することで「苦手より得意を活かす」進路設計が可能になる
・合理的配慮や障害学生支援が整っている大学が増えている
・ノートテイク、試験配慮、通学サポートなど、支援体制が拡充中
入学後も相談できる窓口がある。
・発達特性を理解する社会人になるための準備期間であり、自分の特性を言語化し、人と協働する経験ができる場でもある。
進学前に考えておきたいこと
高校卒業後にすぐ進学するよりも、一度「就労移行支援」「通信制」などを挟むルートもあります。
学習・生活面の自己管理に不安がある場合は、保護者や支援機関と連携しながら進学を考えていきましょう。
結論:必ずしも「必要」ではないが、進学が大きな意味を持つケースも多い
発達特性のあるお子さまにとって大学は、「得意を伸ばし、社会とのつながりを広げる場」として大きな可能性があります。
ただし、進学ありきではなく、本人の希望・特性・サポート体制をふまえて、最適なタイミングで進路を考えていきましょう。
まとめ
発達に凹凸のあるお子様の進路選び|中学・高校受験を総合的に考える
受験はあくまで通過点であり、お子様の人生はその先もずっと続いていきます。
中学受験であれ高校受験であれ、目指す学校に合格することだけが目的ではありません。
目先の進学より「将来どうなってほしいか」を考える
発達に特性のあるお子様の場合、まず大切なのは「将来どのように生きていきたいか」という視点です。
どんな仕事に就きたいか、どんなペースで暮らしたいか、自分の得意をどう活かしていけるか──
そのような将来像に合わせて、中学・高校でどんな経験を積むかを逆算して選んでいくことが重要です。
進学先は「学びの場」であり「支援の場」
お子様にとって学校は、学力をつける場であると同時に、自分らしさを理解され、支えられる場であることが何より大切です。
たとえば:
発達特性に配慮した教育を実践している中学校
学びの自由度が高い総合学科高校
就労や資格取得を意識した専門コースのある学校 など
進学後のサポート体制や卒業後の進路(進学・就職)も含めて、「この環境なら安心できる」と思える場所を探していきましょう。
保護者として大切にしたい3つの視点
1. 情報収集を怠らない
中学・高校ともに、受験制度や学校の対応は毎年変化しています。
各学校や教育委員会、試験機関の最新情報をこまめに確認しましょう。
2. お子さまとの対話を大切にする
お子様が「どのような環境で安心して学べるか」「自分の力を発揮しやすいのはどこか」を一緒に考えていくプロセスが、最適な進路につながります。
3. 柔軟な対応を心がける
希望する配慮や進路が叶わない場合も、代替案を探ることで新しい可能性が開けることもあります。
焦らず、その子に合った道を一緒に見つけていきましょう。
最後に|お子様に合った「選べる進路・受験」を
発達特性のあるお子様にとって、受験は“試験に勝つ”ためだけのものではありません。
推薦入試や特色選抜、中高一貫校や通信制、支援のある私立校など、「自分に合った学び方」を選べる時代になっています。
「うちの子には難しいかも」と思ったときこそ、まずは学校や専門機関に相談してみてください。
きっと、今のお子様に合う選択肢が見つかるはずです。
受験は未来をひらく第一歩。
「どこに行くか」よりも、「どう生きていくか」を一緒に考えながら、進路選びを進めていきましょう。