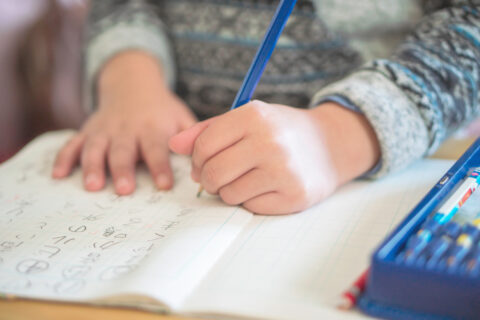目次
こんにちは。
SOLE個別最適学習ラボ編集部です。
今回は「原学級保障」についてお話します。
「原学級保障」とは、大阪府教育委員会が提唱するインクルーシブ教育の考え方です。
障害のある児童生徒も、通常学級で他の児童生徒と一緒に学ぶことを保障するというものです。
文部科学省が2022年4月27日に発出した「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について」という通知(4.27通知)は、そのような大阪府の「原学級保障」と対照的な内容であるために大きな議論になりました。
そこで今回は実際の現場の声や具体例を挙げながら、「原学級保障」と今後の教育現場について考えていきたいと思います。
【大阪】「ともに学ぶ教育」のこれまで

「原学級」とは、通常学級を指し、児童生徒が本来所属する学級という意味で使われます。
「ともに学び、ともに育つ」教育理念のもと、大阪府はこれまで障害のある児童生徒に対しても、「原学級保障」を推進してきました。
ここではまず、「原学級保障」という取り組みそのものについてご紹介いたします。
原学級保障の目的
「原学級保障」とは、大阪府が独自に推進してきた教育方針で、障害のある子どもたちが特別支援学級に在籍しながらも、原学級(通常学級)で同級生と共に学ぶ機会を保障する取り組みです。
この方針の目的は、障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが共に学び、共に育つ「インクルーシブ教育」を実現することにあります。
▼「インクルーシブ教育」の実現に向けて
①共生社会の実現
だれもが共に生きる社会の基盤を築けるように、すべての子どもが同じ教室で学ぶことで、お互いの違いを理解し、尊重し合う力を育む。
②障害のある子どもの自立と社会参加の促進
通常学級での学びを通じて、障害のある子どもたちが社会性やコミュニケーション能力を高め、自立した生活や社会参加への準備を進めることができる。
③すべての子どもへの教育の質の向上
多様な背景を持つ子どもたちが共に学ぶことで、教育現場全体の対応力や創意工夫が求められ、結果としてすべての子どもたちへの教育の質が向上する。
「原学級保障」の背景
1970年代、大阪府では部落解放運動を背景に人権教育が進められていました。
その中で、障害を理由に就学の受け入れを拒否または先延ばしにされたり、教育委員会から特別支援学校(当時の養護学校)への就学を指導されたりした子どもとその親が、地元の公立校への就学を求める運動を起こしました。
さらに、障害のある子どもたちが教育から排除されている事実に気づいた教員たちが、障害児を地域の学校で受け入れる取り組みを始めました。
当時、障害のある子どもたちは特別支援学校に通うことが一般的でしたが、大阪府豊中市では、障害のある子どもたちも地域の学校で学ぶことができるようにする「校区へ帰す運動」が展開されました。
大阪府の「原学級保障」の考え方は、このような取り組みから生まれました。
障害者が健常者中心の学校や社会に適応するための教育ではなく、障害の有無で分けへだてられることのない学校や社会をつくる教育です。
障害のある子どもたちは、特別支援学級に在籍しながらも、通常学級で同級生と共に学ぶことを基本とし、必要に応じて特別支援学級の担任が通常学級に入り込んで支援する「入り込み支援」を受けられるようになりました。
障害児教育は、近年「インクルーシブ教育」と呼ばれることがあります。
「インクルーシブ(inclusive)」とは「包摂的」という意味ですが、大阪府ではこの言葉が広まるずっと前から、インクルーシブな学校づくりが実践されてきました。
大阪府内で実践されている「原学級保障」の具体的な事例
豊中市立南桜塚小学校の「入り込み支援」
概要:支援学級に在籍する児童が、通常学級で同級生と共に授業を受ける。
支援体制:支援学級の担任や介助員が通常学級に「入り込み」、児童の状況や授業内容に応じてサポートを行う。
成果:障害のある児童もクラスの一員として学び、学年が上がるにつれて子ども同士で支え合う姿勢が育まれている。
枚方市の「ダブルカウント」制度
概要:支援学級に在籍する児童が、通常学級にも在籍し、ほとんどの時間を通常学級で過ごす。
支援体制:市独自の予算で「ダブルカウント」制度を維持し、支援学級担任が通常学級に入り込んで支援を行う。
成果:障害のある児童が通常学級で学ぶ機会を確保し、共生社会の実現に寄与している。
大阪市立大空小学校の「全員参加型インクルーシブ教育」
概要:支援学級を設けず、障害の有無にかかわらずすべての子どもが同じ教室で学ぶ「原学級保障」を実践。「すべての子どもの学習権を保障する」という理念のもと、地域と連携した教育を行っている。
支援体制:教職員だけでなく、保護者や地域住民が授業に参加し、子どもたちを支援している。教室内には常に複数の大人が関わり、子ども同士の学び合いを促進している。
成果:不登校や障害のある子どもも安心して通える環境が整備され、子どもたちの相互理解と多様性の尊重が育まれている。
文部科学省の通知

2022年4月27日、文部科学省から「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について」という通知が出されました(以下、4・27通知)
4.27通知には支援学級に在籍する児童生徒の授業時間に関する新たな指針が示されています。
4文科初第375号 令和 4 年4月27日 各 都 道 府 県 教 育 … – 大阪府
4.27通知の概要
この通知は、支援学級に在籍する児童生徒が原学級で多くの時間を過ごすことについて、「通級による指導」と同様であり、不適切であると指摘しています。
具体的には、支援学級に在籍する児童生徒は、原則として週の授業時数の半分以上を支援学級で受けることが求められています 。
大阪府「原学級保障」との対立
4・27通知は、大阪府が長年推進してきた「原学級保障」の理念と対立しています。
「支援学級にいる子どもが原学級で学べているのであれば、籍も原学級におけばインクルーシブになる」というのが文部科学省の主張ですが、そうすると、これまでの大阪府独自のやり方は成り立たなくなります。
「入り込み支援」のようなサポートがあるからこそ、原学級で学べていた障害のある子どもたちは、大半の時間を支援学級で過ごす可能性が高くなります。
もしくは、支援が何もない状態でただ原学級にいることになるかもしれません。
大阪弁護士会は、この通知が障害のある子どものインクルーシブ教育を受ける権利を侵害し、不当な差別に当たる可能性があるとして、通知の撤回を勧告しました。
これに対し、文部科学省は通知の趣旨を正しく理解してもらえるよう情報発信に努めたいと述べ、撤回には応じていません。
保護者の声と現場の反応

大阪では、長年にわたり「原学級保障」で支援を続けてきたため、今回の通知によって従来の支援体制が後退するおそれがあると危惧されています。
特に「先生が減り、教室に居場所がなくなるのではないか」「交流できる時間が減って、友達と過ごす機会が奪われる」という保護者の不安が強く、教育委員会の説明不足に対する不信の声も上がっています 。
保護者の声
支援体制の縮小への不安
「しんどくなった時にクールダウンできる場所や先生が必要で、支援学級に入り続けていたのに、先生が減るのは困る」
「安全な移動の見守りなど合理的配慮を期待して特別支援学級に在籍していた。通知でそれがなくなるのか不安」
原学級保障崩壊による分離教育への懸念
「原学級保障を奪われると、児童が通常学級でただのお客さんになるのがイヤ」
「週の半分以上を支援学級にこもるのは嫌だ」
「障害のある子が“同じ場所にいるだけ”で終わってしまえば、多様性を学ぶ機会が奪われる」
現場の反応
子ども自身の声
「どちらか片方だけとか、少しの時間しかいられないとか、決められるのはいや。お友達と一緒がいい」(9歳)
「大人がいろいろ決めてしまうのが疑問。こども本人の意見をもっと聞いてほしい」(15歳)
社会の視点
大阪弁護士会や国連は「分離教育になりかねない」と制度そのものを問題視しています。
とくに大阪弁護士会は、「特別支援学級で半分以上過ごすよう要求するのは、人権侵害になる」として通知の撤回を勧告しました。
今後の大阪府の特別支援教育の展望

さて、ここまで読んでいただいた皆様の不安を大きくあおってしまったかと思いますが、大阪府の特別支援教育は何も悪い方向にかわるわけではありません。
大阪府における特別支援教育は、今後さらに以下の点で大きく変わって、より多様な子どもたちを包み込む体制へと進化していきます。
支援学校の新設と校舎整備の強化
大阪府は2032年度までに、過密状態にある支援学校の校舎基準不適合を解消することを明言し、2023・2024年度には豊能地域や大阪市北東部などに新設校や分校を設置する予算を確保しました。
これによって、「長時間通学」「狭い教室」などの課題が解消され、子どもたちが安心できる学びの環境が実現される見通しです。
通級指導教室(リソースルーム)の全校展開
大阪市を中心に、「令和8年度までに全小中学校に通級指導教室を設置」という方針が出され、「支援学級が削減され、通級に移行される際の加配」が課題になっているという現状認識も共有されています。
この整備が進めば、特別支援学級と通級の両方が充実し、子どもの個別のニーズに合った選択肢が広がります。
コーディネーター体制・他機関との連携強化
教育・福祉・医療・相談支援が連携する支援教育コーディネーターやスクールクラスター構想が、府内各地で進んでいます。
保健所や医療的ケア関係者との調整によって、医療的ケアを要する子どもたちも安全かつスムーズに学べる環境が整備されます。
教員の資質向上・ICT/アセスメント支援の拡充
箕面市ではすでに「LITALICO教育ソフト」を導入し、個別支援計画の見える化、教材・研修の充実に成功しています。
大阪府全体にもこうしたICTツールの普及が期待されます。
教職員の研修や連携体制が高まり、指導の質が安定することで、支援が必要な子どもへ丁寧に対応する力が底上げされます。
SOLEの記事でもまたご紹介していければと思います。
インクルーシブ教育の理念的拡がり
「ともに学び、ともに育つ」教育を進める資料やガイドラインが府域で整備され、特別支援教育を基盤としたユニバーサルデザイン教育が理念的に根付きつつあります。
今後は教育文化として、学びの多様性や参加の権利が当たり前となる社会に向けて、体制だけでなく意識改革も進みそうです。
子どものためにできること

私たちは支援者として子どもの最善の学びの場を確保するために、情報収集と対話を重ねていくことが求められます。
支援者ができること
教育の現場(教師)と家庭(保護者)の橋渡しを行うことがまず第一に挙げられます。
保護者や教師が抱える不安や疑問を、対話の場を通じて和らげてください。
「子どもにとってベストな環境とは?」ということを、子どもを取り巻く人間全体で考えていきましょう。
子どもの安心を第一にするために、登校・移動に不安を感じる子どもには、まず“安心・安全な居場所”を提示し、その利用を促しましょう。
保護者の皆様へ
まず第一に、子ども自身の声を大切にしましょう。
「どんなときが楽しい?」「何に困っている?」と、お子様の本音を聞きましょう。
「友達と一緒に学びたい」「音読が難しい」といった気持ちを支援につなげていけたらいいですね。
また、学校との定期的な対話・情報共有を心がけましょう。
「自分の子どもにはどんな支援が必要か?」「学級内での様子は?」など、個別面談の機会を活かして質問・確認しましょう。
保護者会なども活用し、情報収集が積極的に行えるといいですね。
まとめ

子どもたちが安心して、得意なことを伸ばし、友だちと共に成長するために――
大阪府は物理的な整備、人的・ICT体制の充実、そして意識としてのインクルーシブな教育文化の確立を一体的に進めています。
これらの動きが連動すれば、今後の特別支援教育は、より「子ども中心」の温かい教育へと進化することでしょう。
制度の変化は確実ですが、それは「安心の質」を高める前向きなステップです。
みんなで支え合いながら、一人ひとりが輝ける学びの未来をつくっていきましょう。
あなたの「声」が、現場を変え、学校をより安心で居心地のいい場所にします。
今は制度の見直しで動揺が広がっていますが、だからこそ一人ひとりの声掛けや行動が、子どもたちの笑顔や安心に直結します。
何かわからないことがあればまず、通われている学校に確かめてください。
もし、ご相談があればいつでも下記にお問い合わせくださいね。