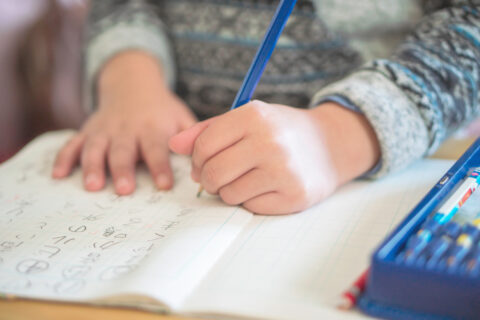目次
こんにちは。
SOLE個別最適学習ラボ編集部です。
・得意なことには時間を忘れて没頭する
・学校の学習が簡単すぎて教室にいることが退屈である
・大人でも難しい専門的な本を読むのが好き
・同世代の友達との会話がつまらない
・常に脳が興奮状態で中々眠ることができない
上記のような特徴をもつ子ども達を「ギフテッド」と呼ぶことがあります。
ギフテッドに関する記事は以下も参照してください。
高IQであったり芸術的な才能に富んでいたりするギフテッドですが、
周囲と違うことによって孤独を感じる場合があります。
今回はギフテッドの子ども達の友達作りに焦点を当ててお話していきます。
最後にはSOLEでのギフテッド児支援についても少しご紹介できればと思います。
ギフテッドとは
これまでにSOLE個別最適学習ラボ編集部のブログで何度か触れたことがありますが、「ギフテッド」という言葉は、国や地域で異なる基準や定義が存在します。
医学的な診断基準はありませんが、欧米、日本はいずれもIQ検査により発見されるケースが多いです。
アメリカの教育省では、「同世代の子どもと比較して、学業・知能・創造性・芸術・リーダーシップのいずれかにおいて突出した能力をもつ子ども」と定義されています。
日本の文部科学省では「ギフテッド」ではなく、「特定分野に特異な才能のある児童生徒」と表記しており、「その才能や認知・発達の特性等がゆえに、学習上・学校生活上の困難を抱えることがある」として、その能力を最大限に発揮できるように支援することを目指しています。
ギフテッドによくみられる行動
ギフテッドの子どもによくみられる特徴と行動の例を参考までに記載しておきます。
・言葉を覚えるのが早い、話すスピードが速い
→すらすらと早口でおしゃべりする
絵本の内容を自分で読む
周囲の口真似が得意で大人のような話し方をする
・並外れた集中力
→ずっと何時間でも同じ遊びができる
何かに夢中になりご飯を食べなかったりトイレに行かなかったりする
・突出した理解力と記憶力
→何年も前に保護者や先生が言ったことを覚えている
電話番号、ナンバープレート、登場人物の名前等を覚えるのが好き
暗記や反復学習が必要な内容をすぐ理解する
・せまく深くの興味関心
→納得がいくまでずっと同じことを調べ続ける
問題集のレベルの高い問題ばかりに取り組む
パズルやゲームにのめりこむ、スキルの習得が早い
・体と心の発達と知能のアンバランスさ
→自分の学年の教室で授業を受けていることが退屈である
先生や友達の言っていることが簡単すぎると言う
・質問や意見が鋭い
→先生や保護者を質問攻めにする
周囲の人が間違っていると指摘する
もちろん、すべての特徴が当てはまるわけではありません。
あくまでも一例であることをご了承ください。
ギフテッド児と過度激動
ギフテッドの子どもの特徴として、過度激動(OE:Overexcitability)と呼ばれる性質があります。
過度激動とは、感情や行動が過剰に表れる状態のことを指します。
ギフテッドの研究をしていたポーランドの精神科医カジミェシュ・ドンブロフスキが導入した概念で、超活動性、過興奮性と訳されることもあります。
ギフテッド児は知的能力の高さが目立ちますが、情緒面や対人関係で困り感を抱えることがあります。
過度激動について知っておくと困り感や課題について整理しやすいかもしれません。
過度激動には5種類あります。
・精神運動性OE 活動的で落ち着きがない。エネルギーが有り余っている。
・感覚性OE 五感の鋭さ。感覚が過敏である。
・知性OE 強い好奇心と探求心。積極的に知識を獲得し、理解しようとする。
・感情性OE 喜怒哀楽すべての感情の起伏の大きさ。感情を調整することが難しい。
・想像性OE 空想の豊かさ。イメージが鮮明である。
参考:ギフテッドとOverexcitability ―肯定的分離理論を通じて― 日高茂暢(2023)
神経の感受性が一般の人より高いことによって、良いことだけではなく、注意力が散漫になったり、頭が働きすぎて夜眠れなくなったり、神経質になったりもします。
情報はたくさん入ってくる上、感情のコントロールが難しいこともあり、本人のせいではないのに、疲れやすいです。
とりわけ、対人関係においてはストレスや不安につながることがあります。
ふつうに生活していても、周囲のあらゆる刺激に過剰に反応してしまい、所属する集団から浮いてしまうことがあるかもしれません。
ギフテッドが友達づくりに苦戦するわけ
ここまで述べてきたように、ギフテッドの子どもは同じ年齢の子どもたちに比べて、特定の分野において突出した才能をもっています。
しかし一方で、対人関係や情緒の面で困りごとを抱えやすく、「ギフテッド 孤独」「ギフテッド 友達がいない」などの内容の記事をみかけることがあります。
保護者様の中にはお子様に友達が少ないことを心配しておられる方もいらっしゃるでしょう。
では、ギフテッドが友達作りに苦戦する理由について考えていきましょう。
同級生との発達段階の違い
ギフテッド児は知識量が豊富で、同級生との共通の話題でも会話が合わないことがあります。
高すぎる知能や能力があるため、物事の考え方や結果が周りと異なってしまい、疎外感を感じるギフテッド児もいます。
そもそも興味関心のあることが違っていたり、マニアックすぎる話題になってしまったりということも起こります。
さらに、難しい言葉を使う、話題がどんどん変わる、というふうに相手が会話をするのに疲れてしまう場合があります。
感受性のユニークさ
先ほど述べた通り、「過度激動」という特性上、高い能力があっても、情緒的な成熟が追い付いていない場合があり、ストレスマネジメントや感情コントロールの面で苦労することがあります。
ギフテッド児は感受性が非常に強く、周囲の微妙な変化に敏感です。
以下に例を示します。
・共感する力が人一倍あるため、相手の気持ちを大きく受け止めすぎて、自分の言いたいことが言えずのびのびとふるまえない。
・皆が気にしないようなささいなこともずっと気に留めて不安に思ってしまう。
・我慢していた感情が爆発し、思い通りにならないことに癇癪を起こす。
・環境の変化に敏感で、切り替えなどが難しく、時間がかかる。
・緊張がさまざまな身体の不調として現れる。
・自己評価が厳しいので、自己批判やうつの症状につながってしまう。
こうした「感受性のユニークさ」のために、ギフテッドの子どもたちは「自分は変だ」と感じたり、不安感や劣等感に拍車をかけてしまったりすることがあります。
周囲からも「神経質すぎる」「大げさである」とみられ孤立し、集団生活に馴染むのが難しい場合もあります。
他人に理解されにくい
ギフテッドは人口の約2%程度に該当するといわれています。
日本では250万人程度いるとされていますが、諸外国に比べてギフテッド教育の理解が進んでいないため、ギフテッドの子どもに対する支援はまだ始まったばかりです。
ギフテッドは「よくできる」児童生徒であるからこそ、そのしんどさがなかなか理解されず、相談できる場もあまりないというのが現状です。
十分な支援がない場では、さぼっているだけ、鼻につく、特別あつかいだ、甘えである、などと思われてしまうことがあります。
非同期発達
ギフテッドの子どもたちは、「非同期発達(Asynchronous Development)」と呼ばれる特性をもつことが多く、このために集団生活での困難に直面することがあります。
非同期発達とは、知的能力、情緒面、社会性の発達が異なるペースで進むことを指します。
つまり、知的発達が高いために、情緒面や社会性の発達や身体的な成長とのバランスが取れていない状態です。
得意な分野では非常に高い能力を発揮したり、幼いころから難しい言葉を理解出来たりするために、情緒面や社会性も育っていると思われがちですが、情緒面や社会性は年齢相応かそれ以下であるので、友達と遊びにくくなります。
さらに、ここにこだわりの強さなどが加わるとよりトラブルが起きやすくなります。
また、トラブルが増えると本人の自己肯定感が下がり、本来の自分を出せなくなるので、ストレスになったり、集団で過ごせなくなったりします。
非常にIQの高いお子様は、理解はできても身体が追い付かない現象(身体的な成長とのギャップ)で苦しむこともあります。
ギフテッドの気の合う友達の見つけ方
ギフテッドは友達や先生から離れてひとりで黙々と1つのことに取り組むことも多く、ひとりでも大丈夫だと思われがちですが、実際そのようなことはありません。
わたしたちも学校や職場、家庭の中、あるいは外で、趣味や好きなことについて話せる友達がいれば心強いはずです。
ここまで読んでくださったみなさんであればおわかりかと思いますが、ギフテッドの子どもたちも自分たちがのびのびできる居場所を欲しています。
「Vulnerabilities of highly gifted children」というギフテッドの孤立について書かれた論文では、以下のように記載されています。(下記日本語訳)
『ギフテッドが学校の中で上手くやり、その後の人生においても成功するという人生の成功は、ギフテッドの子にとって自然発生的なものではなく、環境によるサポートが大きく影響している。』
このことからも、ギフテッドにはサポートしてくれる人や、一緒に学んだり遊んだり、ときには相談できたりする仲間の存在が重要であることがわかります。
ここでは、どのようにしてギフテッドが気の合う友達を見つけていくかを考えていきましょう。
発達障害グレーゾーンで、不登校で、ギフテッド。「浮きこぼれ」君と勉強
自己理解を深める
ギフテッドは高い能力をもっています。
まず、自分自身の能力、特性や才能、そしてそれらがもたらす影響を客観的に理解することからはじめていきましょう。
さらに悩んでいること、困っていることについても自分で理解し、何が原因でストレスを抱えてしまっているのかを考えてみましょう。
自己理解を深めることで、ギフテッドは自分のありのままを受け入れ自信をもつことができたり、自分の強みを活かして社会に貢献できる方法を考えられたりします。
ストレスについては振り返り見つめなおすことで、人に頼る、専門家に相談する、他の方法でカバーする、等の対処法を見つけ、社会で困らない程度の苦手にすることができるかもしれません。
多くのギフテッドは、自分の特性に気づかずに生きづらさを感じています。
自己理解が進むことで、自分の強みや弱みを認識し、適切な対策や環境調整が可能になります。
具体的には、自己理解を促進するためのカウンセリングやメンタリング、自己受容を支援するプログラムの導入が有効でしょう。
ソーシャルスキルの向上
つぎに、ソーシャルスキルの向上です。
ソーシャルスキルとは、対人関係における目標を達成するための適切なコミュニケーション・行動・思考の総称です。
簡単にいうと、「ほかの人に対する振るまい方やものの言い方」のことです。
ギフテッドが集団生活になじめない原因としてソーシャルスキルの問題は大きな割合を占めています。
ギフテッドが適切なコミュニケーションをとることができるようにするためには、共感力やソーシャルスキルの向上支援が必要です。
ソーシャルスキル・トレーニング(SST)などで、相手の気持ちを理解して流暢に会話のやりとりをする技術を身につけたり、場面や状況に合わせて相手にどのように伝えるのが適切かということを学んだりすると、社会で過ごしやすくなるでしょう。
また、ギフテッド自身も自分のコミュニケーションのスタイルを理解し、柔軟な対応ができるようになるといいですね。
※ソーシャルスキル・トレーニング…対人関係で問題行動や心理・社会的問題を抱えている人たちを対象に体系的にソーシャルスキルを教えるもの。
いろいろなコミュニティに属す
何度も申し上げています通り、ギフテッドの特性は、周りの人からは理解されにくいことが多く、孤独感を感じることがあります。
しかし、家庭や学校以外での居場所、ギフテッド同士のコミュニティや年齢を問わない興味関心の分野の団体に所属することで、本人の孤独感や居心地の悪さが解消されることがあります。
同じギフテッドの子どもたちが集まるコミュニティは、ギフテッドの特性を持つ子ども同士や、ギフテッドの子どもを持つ親が共感し合える居場所となります。
それだけでなく、ギフテッド同士のコミュニケーションでソーシャルスキルの向上につながったり、同じレベルで話せる存在があらわれることで学習意欲の向上につながったり、ギフテッド教育や支援についての情報交換の場となったり、お互いにとって良いことがうまれます。
以下にギフテッド向けの活動をされている団体をご紹介いたします。
残念なことに、日本は諸外国に比べてギフテッドの認知度がまだ低いのが現状ですが、調べると近年はオンラインサロンなども開講があったりします。
もちろん、ギフテッド向けの団体や集団ではなく、本人の興味や関心のあることのコミュニティに属するのもいいかと思います。
SOLEのギフテッド向けプログラム
現在、個別最適学習プログラムSOLEにはさまざまな個性をもったお子様たちが相談に来られています。
検査を行い、学年相当ではなく、お子様一人ひとりに合わせた学習方法を提案させていただいております。
こちらのオーダーメイドのプログラムは皆様から非常にいい評価を受けています。
最近はギフテッドのお子様がいらっしゃるご家庭からのお問い合わせも増えてきております。
そのような中で、集団でのコミュニケーションワークや個別でのレベルにあった学習のご要望が多くあがっていました。
そこで私たちSOLEでも、ギフテッド向けのプログラムが始動する運びとなりました。
内容といたしましては、
・小集団での居場所作りと自己実現
・自分の興味関心のある分野の探求学習
などを予定しております。
2025年秋ごろにプログラムとしてご提案できるようにしておりますので、ご期待ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
ギフテッドについて少しでも理解が深まればいいなと思い、この記事を作成いたしました。
ギフテッドの社会的孤立を防ぐためには、まず彼ら自身が自分の特性をわかること、その特性を活かせるような教育が重要であることはもちろん、彼らが安心して自分を表出できる環境の提供や理解あるコミュニティの形成が必要です。
具体的には、ギフテッド専用の教育プログラム作りや、交流機会の増加などが求められます。
SOLEでは学校内容ではなく、その子どもに応じた学びを提供いたします。
さらに、学習プログラムに加えて、社会的スキルの育成、他者とのコミュニケーション能力の向上も行っていく予定です。
少しでもご興味をもたれた方は一度ご相談だけでもお電話ください。
また、保護者様の中で、本人たちとどうかかわっていけばよいのか、この先友達ができなかったらどうしよう、などと悩んでおられる方も一度SOLEにご連絡ください。
彼らが本人らしく生きていけるように家庭および学校や職場でのサポートを一緒に考えていきましょう。